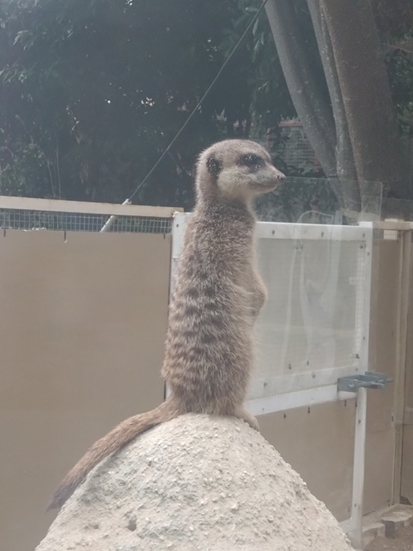(シバザクラと武甲山・埼玉県秩父市の羊山公園、by T.M)
MBS NEWS 7/3
大阪・関西万博で相次ぐ、海外パビリオンの工事費未払い問題。新たにアメリカ館の工事に携わった下請け業者間でも未払いが起きていることがわかりました。
連日、長蛇の列ができる人気パビリオン「アメリカ館」。千葉県の内装業者は3次下請けで建物の壁などの組み立てを請け負い、去年11月からことし3月まで、工事を行いました。
しかし、この内装業者によると2次下請けからの入金が2月末で途絶え、約2800万円が支払われていないということです。
業者は取材に対し、「未払いですね。まさかですよね。こんなことがあっていいのって思っている」と話します。
未払いの工事費について一部だけでも早く支払ってほしいと発注元の2次下請けと交渉していましたが、その最中の5月に突然、その業者が破産。工事費の回収のめどが立たなくなっているということです。
博覧会協会は相次ぐ工事費の未払いについて「私たちができるのは行政の相談窓口などの紹介」だとしています。
これ、けっこう根が深い問題ですよ。取り敢えずは国交省何やっているんでしょうかね。工事の施工代金のトラブルは国交省が管轄するはずなんですけど・・・
私が労働基準監督官をやっていた時代には、このようなトラブルはありませんでした。第3次下請けだろうが、第4次下請けだろうが、賃金未払が発生した時に、元請けに連絡すると、元請けは出面(でずら)と賃金額を確認して、立替え払いをしてくれました。理不尽と思えることでも実によく言うことを聞いてくれました。
元請けがこんなに監督署に協力的なのは、自社が施工した現場では法違反をださないという元請けの法遵守の意志がある訳ですが、実は他にも理由があって、実利の一面もあります。
下請けの賃金不払いを、監督署の要請にもかかわらず、元請けがスルーした場合は、監督署は国交省に通報するシステムがあり、その場合は、元請けは数か月から数年間にかけて、公共工事の受注ができなくなるのです。請負高何千億もの公共工事の受注に影響するくらいなら、下請けの未払賃金くらい自分たちで払ってしまえということです。
因みに、この公共事業の入札禁止という奥の手は、影響が非常に大きいものです。労災事故が多発した場合も入札禁止になるのですが、事故が起きても元請けには連絡しないという下請けの労災隠しの原因にもなるという負の側面もありました。
ですから、建設会社で発生する賃金未払は、「公共工事の入札」に直接的にも間接的にもまったく関係のない、零細企業でのみ発生しました。
さて、今回の万博での賃金未払が、大きな問題となった背景には
海外の企業が元請け
となったことが大きな原因です。彼らには、「今後、日本での公共工事の受注」など、なんら関係がないのです。従って、彼らが直接契約した一次下請けとの民事的なやり取りがすべてで、二次以下の会社の経営状況などしったことではないのです。
今後は、このような海外の建設会社の工事が日本国内で増えていくと思います。そうすると古き良き時代の元請け・下請けの関係は崩れるものと思います。またひとつ、世知辛い世の中になりそうです。