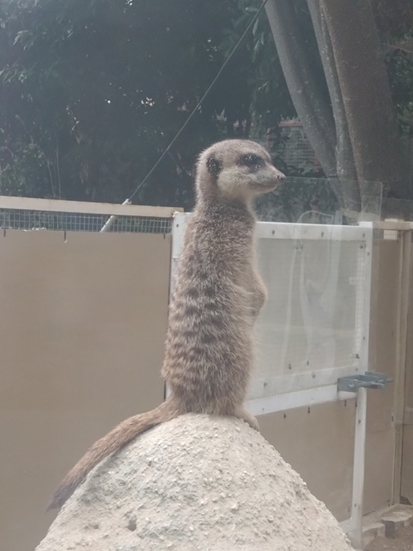
(ミーアキャット・智光山公園こども動物園、by T.M)
先月、私が衛生管理者の受験準備講習会の講師をしていた時のことです。ある受講生が質問をしてきました。
「カード穿孔機って何ですか」
その受講生は、古い衛生管理者試験の試験問題を見て、そういう質問をしたようでした。令和4年に、事務所衛生基準規則が改正され、「騒音防止対策の事例として紹介されていたカード穿孔機の業務」が法条文からなくなりました。
(新)事務所衛生基準規則第十二条 事業者は、タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するものを、(略)専用の作業室を設けなければならない。
(旧)事務所衛生基準規則第十二条 事業者は、カード穿孔機、タイプライター等の事務用機器で騒音を発するものを、(略)専用の作業室を設けなければならない。
実は、私は受講生からこの質問をされるまで、「カード穿孔機」という文言が法律から削除されていたことを知りませんでした。
この時の事務所衛生基準規則の改正については、「事務所には男女別のトイレを設置しなければならない」から「マンションの一室を利用した職場では男女共用のトイレでも良い」という改正が含まれるもので、そこそこ話題になったものでしたが、その法改正個所の盛り上がりと比較し、「カード穿孔業務の削除」はまったく話題になりませんでした。(厚生労働省製作のリーフレットにも記載がなかった)。
「カード穿孔業務」とは、フロッピーディスク等ができるまでは、コンピューターのプログラミングは、紙カードに穴をあけ、それを機械が光をあて読み取り、外部データーとして保存したものでした。分かりやすくいうと「マークシート」用紙について、黒く塗るところを穴をあけるのです。(「マークシート」も「タイプライター」も、多分もうすぐ死語になるでしょう)。この業務は、40年前にコンピューターに関連した仕事をしていた者にとっては、当たり前のように認識していた業務でしたが、その業務を指す文言が、静かにこの世から消えていくことは、当時を知る者としてはけっこうショックなものです。
そういえば、こんなこともありました。私が非常勤で勤務している某労働安全衛生団体のHPから、なんと団体の電話番号が消されたのです。何でも、業務に無関係な電話が入ってくるから煩わしいとのことでした。私のような年齢の者については信じられないことです。でも、なんかこれが現在では、当たり前のことのようです。何より、現代の若者は「電話の応対の仕方」が分からないとのことです。
私たちの世代の常識では、「ウィンドウショッピングしてくれる方」もお客さんであるという認識でした。だから無用の電話もかけてくれるだけ有難いと思っていました。でも、現在では「実際にお金を出して購入してくれる方」のみがお客さんという認識です。オンライン・ショップが流行る訳です。リアル店舗の商店街の散歩を楽しむことは、高齢者の感傷にすぎないのでしょう。
もはやメールだけが通信手段と思っていたら、ふと気づくことがありました。メールで労働相談に乗っていたら、高確率で「ありがとうメール」が届くのですよね。けっこうこれは嬉しいものです。
どうやら、今の若いものは、若い者なりの礼儀作法があるようです。老人にはなかなか気づかないところに思いやりの気持ちが生きているんでしょうね。