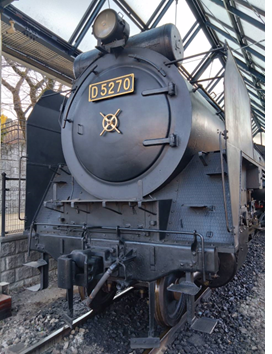(シラカバと紅葉・上州武尊山山麓、by T.M)
11/29 読売新聞
神奈川県内で昨年、トラックやバスなどの車両を使用する事業者の8割超で労働基準関係法の違反があったことが、神奈川労働局のまとめで分かった。運転手の担い手不足や時間外労働の制限で輸送能力が落ち込む「2024年問題」も懸念されるなか、職場の環境改善は大きな課題となる。
発表によると、県内162の事業所のうち84・6%にあたる137事業所で、労働基準法や最低賃金法に違反があった。違反の内訳(重複あり)は、労働時間に関する内容が97事業所(59・9%)、時間外手当の未支給などが40事業所(24・7%)と続いた。時間外労働が1か月で222時間となるドライバーもいたという。
違反した事業者数は、20年が125事業所、21年が104事業所と高止まりしている。労働局の担当者は「人手不足が常態化し、しわ寄せを受けているドライバーもいる」と分析する。
業界の労働時間を巡っては、来年4月から「働き方改革関連法」により、時間外労働時間が年間960時間に制限されることで、運転手の長時間労働の是正が期待される。ただ、物流停滞による社会への影響のほか、賃金減少などによってドライバーの人手不足が進むおそれもある。労働局監督課の哘崎雅夫課長は「減った労働時間分の賃金を補う仕組みが必要だ」と指摘する。
2024年問題って、運送業も建設業も同じように考えられているけど、本質的に違う問題があるんですよね。
建設業は、例えば万博の問題が典型的なんですが、建設業自体が「一過性の受注量の増大」をあてにして、中々「人を増やすことに踏み切れない」という問題があるんです。人を増やそうと思えば、奥の手があります。「外国人労働者」の雇用です。
運送業は、その手が使えないんです。現行の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」では、トラック運転手やタクシー運転手について技能実習生という名の外国人労働者が従事できないんです。だから、慢性的に人手不足となるのです。
私自身は、これ以上外国人労働者が増えることには懐疑的です。「文化の違う人が増えることがなんとなく不安だ」という思いもありますし、日本人労働者の賃金等労働条件が低くなってしまうのではないかという危惧もあります。しかし、なによりも
「外国人労働者及びその家族について、日本人と同じ権利を持つこと。医療、教育等の社会補償は当然であり、生活保護についても認めること」
について、日本人は覚悟ができていないのではないかと思うからです。
ただ、もし外国人が働く制度が変わり、トラック運転手やタクシー運転手へ外国人労働者がそこに雇用されることとなったら、けっこうWinWinの制度なるかもしれません。
農業は、労働基準法により「残業しても割増賃金を支払わなくてもよい」ということになっています。経済面の理由のみで日本で働きたい外国人労働者にとっては、運送業で働く方が合理的だと思います。