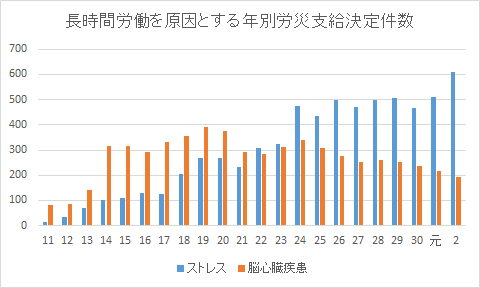私の親友である、某地方労働局安全専門官T.M氏から、秋の便りが届きました。
紅葉狩りに栃木県の瀬戸合峡、 川俣湖に行ってきたそうです。(人々は、コロナ生活に戻りつつあるようです。
まとめて、掲載します。




朝日新聞・11月4日
住宅建材大手の東リ(兵庫県伊丹市)の工場で建材の製造などを行っていた労働者が、「偽装請負」の状態で働かされていたと訴えた訴訟の控訴審判決が4日、大阪高裁であった。清水響裁判長は、偽装請負には当たらないとした一審・神戸地裁判決を取り消したうえで、同社と直接の雇用関係にあると認め、未払い賃金の支払いを命じた。
2015年施行の改正労働者派遣法で、偽装請負の場合、派遣を受けた企業側が労働者に直接雇用を申し込んだとみなす「みなし制度」が導入された。このみなし制度を適用した今回の判決は、企業の雇用形態について、改めて見直しを迫るものとなりそうだ。
原告は東リから業務を請け負っていた会社の社員だった5人。東リの工場で建材の製造や検査をしていた。17年に両社の契約が終わり、業務は別の人材派遣会社に引き継がれたが、5人は解雇されたため、東リと直接の雇用関係があることの確認を求め、提訴した。
労働基準法を扱っているコンサルタントとしては、これは大きなニュースです。今後も、このようなケースが増えるのではないでしょうか。
「業務請負」から「派遣会社」に業務の形態がシフトした訳ですが、この前後に工場内の指揮命令方法が変わってなければ、そもそも最初の「業務請負」についても、元請会社の職員が請負会社の労働者に直接指示をしていたのではないかと思えます。そのような事実が明らかになったので、今回のような判決になったのでしょう。
働く人にとっては、非常に良い判決だと思うのですが、元請けが偽装請負を疑われるのを嫌がって過度に神経質となり、安全管理の現場では非常に困ってしまうことも起きいます。例えばヘルメットです。
建設現場でヘルメットをしていない労働者がいたら、元請は厳しく叱責し、場合によっては出入り禁止とします。これは元請けの工事現場における安全衛生の統括管理に係る権限が労働安全衛生法によって明確に規定されているからです。ところが工場等の製造業の現場では、元請けにその「統括管理」の権限がありません。ですから、「ヘルメットをしなければならない、天井クレーンが使用されている工場内において、ヘルメットをしていない下請け労働者を元請け職員が現認しても、『直接指揮』することがためらわれて見過ごされてしまう」という現象が起きているのです。
特に深刻なのはフォークリフトの使用時においてです。フォークリフトは製造の現場等によく使用されていますが、同じフロアでの作業員との接触事故が常に危惧されています。ところが、フォークリフト運転手と作業員が違う下請け会社に所属している場合等について、元請けが両者に「直接指揮」ができないとめ、両者の話し合いによる解決しかなく、無秩序になっている現場があるのです。(逆に言うと、元請けが「直接指揮できない」を言い訳にして何もしていない)。
それでも、製造業の工場はまだましです。「建設業」の現場ほどではないにしても、まだ、「下請けを含めた安全衛生協議会」を作る義務等を含めた、「統括管理」の労働安全衛生法上の義務があるからです。
無法状態なのが、大手インターネット通販会社の倉庫内業務です。大手インターネット通販会社のなかのピッキング作業等は、どこまで大手通販会社に安全管理の責任があるのか、または管理をまかされている大手運送会社に責任があるのか、個々の運送会社や業務委託会社に責任があるのか判然としません。そこでその倉庫内では事故が絶えない訳です。
一応、労働安全衛生法第29条では、元請けが請負会社を指導するように規定されていますが、この条文は「罰則」がないもので、どこの会社も守らないのです。
この労働安全衛生法第29条の規定と、「元請けが直接指揮をすることによって生じる偽装請負の可能性」は、今後検討されなければならないものです。しかし、現実に事故が多発している現実において、「労働安全衛生」の互いに声かけ等については、「直接指揮」や「パワハラ」に該当しないでせっきょくてきに行うという風潮になってほしいものです。