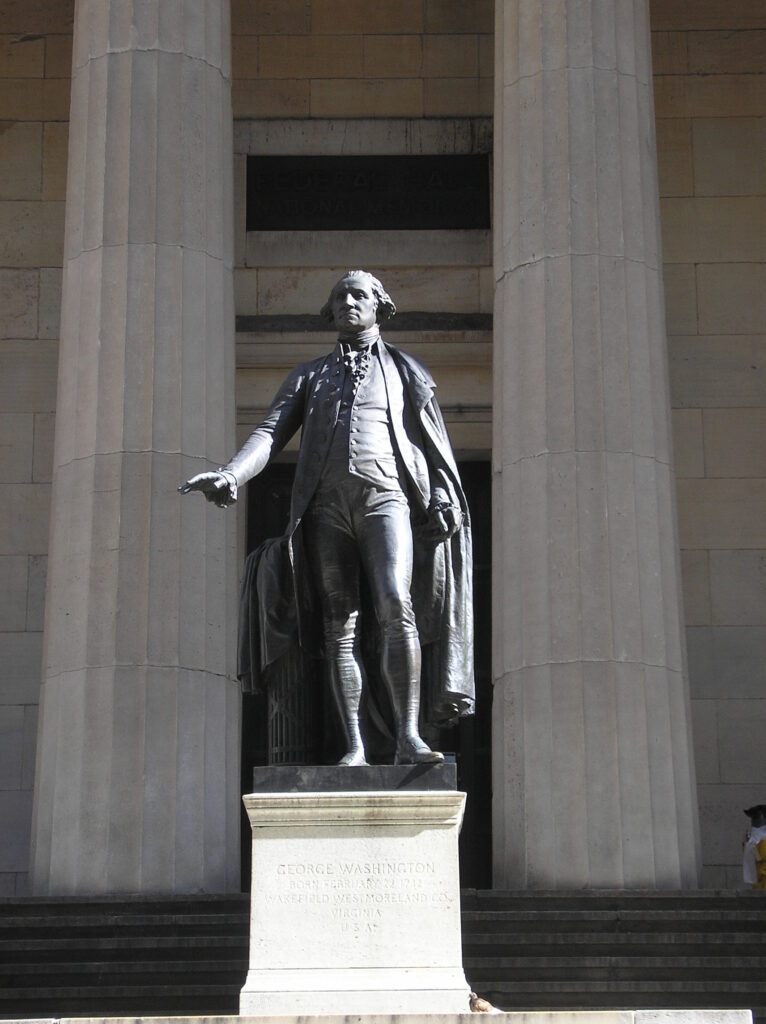(伊豆市・梅木発電所導水橋、by T.M)
たいへん興味深い記事がyahooニュースに掲載されていました。長い記事だったので私が要約したものを紹介します。
DIAMOND ONLINE 3月21日
1. 今さまざまな国で「つながらない権利」が注目されています。「つながらない権利」とは、勤務時間外に仕事やメールの連絡が来た場合に、労働者がその応答を拒否できる権利のことをいいます。フランスでは2017年法制化されその後イタリアやメキシコでも法制化、アジアにまで法制化を検討する動きが広がりつつあります。もともと通信技術の発達により議論が進んでいた中で、コロナ事情によりテレワークが浸透したこともつながらない権利に対して議論が進んだ要因といえるでしょう。
2.「あの件どうなった?」
食品メーカーに勤務する佐々木さん(仮名)は、休日の家族とのランチ中に上司から入ったLINEに困惑したといいます。
佐々木さんは、どうなったと聞かれても資料を確認しないとわからないし、実際に家に戻ってLINEを返したところ、調べて返すまでに1時間弱かかったというのです。
3.つながらない権利が法制化することで考えられることの一つに、企業のサービスの低下が考えられます。イージとしては、携帯電話が普及する前の時代に近いでしょうか。メールや電話などの連絡が取れないことで業務を進めることができず、翌日以降に持ち越されてしまうことが想定されます。持ち越せるものであればよいのですが、今までなら対応できたことが「本日は担当者が不在にしておりまして…」と遅れてしまうケースや、クレーム対応が迅速にできなくなる可能性があるでしょう。
4.つながらない権利をめぐってはさまざまな事情があり、海外では法制化される動きが広まりつつあります。今後、日本でも本格的につながらない権利の法制化が検討されることも、ないとはいえません。今からつながらない権利への対応を始めておくことは、今後の働き方を見直す意味でも有用といえるでしょう。
5.テレワークが定着する中で、厚生労働省から2021年3月に「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(以下ガイドライン)が公表されました。つながらない権利に関係するところでは、ガイドライン内で以下のように記載されています。
「・時間外、休日又は所定外深夜 (以下「時間外等」という。)のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。」
「・テレワークにおいて長時間労働が生じる要因として、時間外等に業務に関する指示や報告がメール等によって行われることが挙げられる。このため、役職者、上司、同僚、部下等から時間外等にメールを送付することの自粛を命ずること等が有効である。」
ざっとこのような記事ですが、これはたいへん難しい問題だと思います。
まずは基本的には、「つながらない権利」は、「当然の権利」だと思います。仕事の連絡を時間外にしてくる方がおかしいのです。会社等からのメール・LINE等は時間外は無視してかまわないし、また「しないことがマナー」という一般常識を徹底させるべきでしょう。
でも困るのが、「事故対応時の連絡」。東日本大震災の数か月後まで、某電力会社では職員に対し、次のような業務命令を出していたという噂を聞いています。
「休日であっても、県外に行ってはいけない。会社からの緊急連絡に対処できるようにしておいてくれ」
この業務命令が事実であったなら、明らかな労働基準法違反です。でも、あの時の状況では仕方がなかったのかなとも思います。
この「つながらない権利」と「緊急連絡」の問題を解消する方法は、私は「労働」という概念を再検討することではないかと思います。すなわち、
「時間外の会社からのメールを受取った場合、それを読む時間が例え数十秒であったとしても、それは『時間外労働』となる。メール対処に費やした時間にはすべて残業代が支払われるべきである」
このような考えを徹底すべきだと思います。
上司は、時間外に部下にメールを送付する時は、「残業を命令している」という意識を持つべきです。